-翠玉の果実-
そう呼ぶにはあまりに淡く幼く青かったその気持ちにつける名前を、
拙い俺の語彙は持たない。
けれど・・・
「憧れ」と片付けるには熱すぎて、「親しみ」で済ますには深すぎた
その想いを一言で表すなら・・・
それはやはり、紛れもなく「恋」だった。
あれから一体何年経ったのだろう。
遠い夢のようにぼやけた記憶の中で笑う女は、それでも今尚、俺の心の片隅に
住み続け、時折こうして、俺をあの過ぎた日々へと誘う。
「ねえ・・・・・・・隊長さんって、普段からまるきりダメって訳じゃないんでしょ?
やっぱ、あたしの所為かな。・・・交代、したほうがいいよね。
まだ誰か他の子が残ってるかもしれないし、ちょっと階下見て来ようか?」
「いいって。気にすんな。別にあんたが悪いんじゃねえよ。男って奴は、
これで案外デリケートな生きもんでね。見境なくサカりまくったかと思うと、
ちょっとした拍子にいきなりこうなる事もある。
・・・・あんたが嫌じゃなけりゃ、このままちょっと、話し相手にでもなってくれよ。」
「いいけど・・・・・・何か悪いね。部下の人たちの分も、多すぎるくらい御代を
頂いてるっていうのに・・・・・・・・・・。」
俯いた女の肩を背中から抱き寄せ、俺は笑いながら薄く汗ばんだうなじに唇を押し当てた。
きめ細かい肌と、細い背に似合わぬ豊満な乳房は、本来ならば充分すぎるほど
欲情に値するシロモノであるはずなのに、今夜は俺の中の「男」はしっかりと鍵を下ろし、
一切の昂ぶりを催しはしなかった。
薄いシフォンのカーテンが生温い風に煽られ、ベットサイドでふわりと揺れ、
開け放ったままの窓から、ジジ・・リリリ・・・と虫の鳴き声が響く。
天井に設えた年代物らしい扇風機が、むっとする夏草の青い薫りを含んだ空気をかき回す、
娼館の二階の角部屋。
「じゃあ、何かお酒でも持ってくるわ。少し待っててくれる?」
「お、いいね。でも・・・・酒より出来れば・・・・なんてあるかな?
こういう細くて背の高いいグラスに、氷いっぱい入れて、サ。」
「あるけど・・・・そんなのでいいの?お酒でなくて?」
微笑みながら頷いてみせると、困ったような視線を向けて首をかしげたまま、女がそっと
部屋を出て行った。
まったく・・・・あんな仕草まで、可笑しい位によく似てやがる。
マイッタ。
失敗したなあ。
これからは何があっても・・・黒髪で、デコが広くて目の丸い、小柄な童顔の女だけはよすとしよう。
俺の身体って奴は、俺自身が思うより、ずっと繊細に出来てやがるらしいな。
海賊の一連隊を預かる男が、度がすぎるロマンチストなんてシまらねえ。
俺は苦笑を禁じえないまま、そっとサイドテーブルから煙草を手にとり火を点けた。
・・・・・・今頃・・・・どうしているのかな・・・・・・。
吐き出した細い煙は、天井に上りきらないまま攪拌され、ほの白く浮かんだ面影と共に、
あっというまに窓の向こうの暗闇に溶けて流れていく。
そう、あの日も今夜と同じくらい・・・・・・・嫌になるほど暑かった・・・。
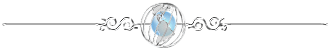
あの日の午後も、あいつはいつものように一人カウンターに腰掛けて、何やら帳簿を
付けていた。
「マキノ、マキノ!何か食べる物あったらくれよ。
今日はこれからまたアイツらに、次の航海に連れてってくれるように
頼みに行くんだ!ちゃんと腹ごしらえしていかないと、いざって時に
力が出ねえからさ!!」
店内に走り込むやいなや、犬っころみたいに纏わりつくルフィに、あいつは
優しげに目を細める。
そんな顔をする時のあいつは、いつもよりほんの2割増といった程度だが、
ちっとばっかし眩しく見える。
ここは、フーシャ村の港に一番近い酒場、「PERTYS BER」。
4年前にあいつの親父が死んで、まだ18だったあいつがこの店を継ぐと言い出した時、
村長以下、村の人間は一人残らず反対したらしい。
場所柄、海の荒くれ男どもが大勢集うこんな場所を、こんな小娘が一人で切り盛りするなんて
絶対に無理だと誰もが思っていたのだ。
しかし、あいつは皆の不安をよそに、その裏表のない真摯な接客態度と、本人曰く
「嫌な事は一晩寝れば忘れるの」という、その外見からはおよそ想像もつかない単純で図太い
神経をフル活用し、意外に上手く店を繁盛させていた。
「・・・・・エースは行かないの?ルフィはもう、船着場に走っていったわよ。
あの子ったら近頃は、あの赤髪の船長さんの所に入りびたりね。」
自分の弟の弟の食い散らかした皿を、営業時間外のあいつに運ばせるのはしのびなく、
せっせと屑を集めて運ぶ俺を、あいつが少し離れた場所から、優しく見つめ返している。
「別に・・・・。俺はルフィほど、あいつらに興味はねえから。
あのシャンクスってのがどうも胡散臭くて、俺・・・・好きになれねえ。」
「フフフ・・・。何を置いても『エース、エース』だったあの子が、あの船長さん達が
この村に来てからこっち、寝ても冷めても『シャンクス、シャンクス』だものね。
あなた、寂しくなったんでしょ?」
「くだらねえこと言うなよ。俺たちは確かに兄弟だし、2人とも将来は海賊になるって
決めてるけど・・・・だからって一緒の船に乗って一緒に海賊になる訳じゃないぞ。
仲良しごっこはまっぴらごめんだ。それぞれが自分の信じた道を行けばいいって、
俺は思ってる。それはきっと、あいつだって同じだろ。」
「エース・・・随分大人びたこと言うのね。小さかったあなたが、もう10になるんですものね。
・・・また少し背が伸びたんじゃない?」
そう言ってスツールから立ち上がったあいつが、にこにこと微笑みながら、俺の瞳を
覗き込んだ。
前髪の分け目と広いおでこが目の前に迫って、何故か言い様のない息苦しさを感じた
俺は、フイとあいつの横をすり抜け、テーブル席の椅子のひとつに腰を下ろした。
「でも・・・変わらないところもあるわね。」
「あん?」
「ルフィはここへ来るとしょっちゅうテーブルに座ったりして平気なのに、あなたは絶対に
そんな事しないでしょう?」
「テーブルは飯を食うところだ。ケツなんかのっけていい場所じゃねえ。」
「うふふ。わたしね・・・エースのそういうところが大好きよ。あなたがこの先、どんなに
背が伸びて、外見が大人に変わっても・・・きっとそういう、あなたの真っ直ぐで綺麗な部分は
変わらないって、そんな気がするの。」
「・・・勝手に決めんなよ。」
屈託のない笑顔が訳もなく居心地悪くて、俺は窓の向こうへと視線を外した。
向かいの家と挟んだ畦道をほんの数メートルいけば、もうそこは海。
やるせないほど快晴の空と、透明な藍の水との境目がやけにチラチラと輝き、目に痛む。
あ・・・・・・・また、だ。
またあの、眩暈のような違和感が、じりじりと足元から這い登ってきた。
ガキの頃から見慣れたその風景が、まるで生まれて初めて目にする異国の街並のように、
不意に姿形を変えて視界に飛び込んでくる。
今まで・・・・空の色ってこんなに濃かったか?
海ってこんなに光ってたか?
そしてあいつは・・・・・・こんなに細くて白くて、いい匂いがしてたか?
自分以外のこの世のすべてが、俺の知らない間によく似た偽物と置き換えられ、
俺一人が異物になってしまった気がする、あの感じ。
近頃それがやけに多くて・・・・・・・・・・・・とても、疲れる。
「マキノ・・・・・・・。昨日、おまえ・・・・・・・。」
「え?なあに?」
いつ間にかカウンターに入ったあいつが、ガラスのピッチャーを持ったままくるりと振り返った。
語尾の「に」の発音の形を残したままの、笑ってるみたいなあいつの口元に目が吸い寄せられる。
薄いピンクに彩られた唇の間から、ほんの少しだけ覗く前歯は真っ白で、まるっきりハッカの
キャンディーみたいだ。
あれを舐めたら・・・齧ったら、どんな味がすんだろ。
・・・・・・・・・あの男なら、知っているのか。
「なんでもないよ。」
「言いかけて止めないでよ。ヘンな子ねえ。」
「なんでもないって言ってるだろ。」
クックッと鳩みたいに首を竦めて笑いながら、目の前のテーブルにふたつ、冷えた
ライムジュースが置かれた。
カランと氷が揺れて、俺の焦りそのままに、グラスの外側をしとどに水滴が流れる。
馬鹿ヤロウ・・・・言えるわけねーだろが。
・・・「ゆうべおまえ、シャンクスとキスしてただろ?」なんて・・・・・。
「飲まないの?」
「今飲もうと思ってたとこだよ。」
俺はグラスを持ったまま、液体を通過する毎、あいつの白い喉が微かに上下するのを、
ただぼんやりと不思議な気持ちで眺め続けていた。
ストローの淵につけられた、ちいさくすぼめた唇が濡れてる。
虫・・・花・・・いや、違うな。
つやつやと光ってやたら柔らかそうなそれは、まるで今まで見たことのない、
新種の果物みたいだ。
薄い皮を噛み千切ったら、破れ目からたっぷりと蓄えられた水蜜が、溢れて飛び散ってしまい
そうで・・・・・・。
飲み終えたグラスを素早く傾けたかと思うと、つるりと氷の一片を吸い込んで、あいつが
悪戯っぽく笑った。
他の人間がいるところでは絶対にやらないけれど、あいつはコレが大好きなのだ。
お行儀悪いから、真似しちゃダメよ。
そう言いながらジュースを飲んだ後は、いつもひとりで嬉しそうに、こうしてがりがりと
氷を噛み砕いてる。
ガキみてえ。
こうしると、こいつはほんとにガキみてえだ。
それなのに・・・・
昨夜寝る前になって、急に村長のオヤジに使いを頼まれてたのを思い出した俺は、慌ててあいつの
店に走っていた。
次の日の朝で構わないはずなのに、わざわざそうしたのは、そういう事を後回しに出来ない
俺の難儀な性格の所以か、それとも・・・・どこか心の隅で感じてた、胸騒ぎのためだったのか。
ドアから細く漏れる明かり。
裏窓に映ってる、重なるふたつの影。
シャンクスの腕の中で目を閉じたあいつの横顔は、これまで嫌と言うほど見てきたあいつと
全然違ってて。
胸に置いた2本の手とか、上に向けた顎の線とかも、全然全然、違ってて。
マキノも女なんだなって、思った。
あたりまえだけど・・・そう思ったんだ。
キスって・・・・絶対変だよな。
口と口をくっつけるのが「愛してる」のシルシだなんて、どこのどいつが決めたんだろう。
耳と耳じゃなく、鼻と鼻でもなく、口と口。
他人の唾をくっつけられるのは気持ち悪いのに、キスならいいのか?
「あなたのことは好きだから口をくっつけても汚いと思わないよ」って、そう言いたいのか?
わかんねえ。
どうして・・・人はキスなんてしたいと思うんだろ。
どうして・・・・・・
マキノはシャンクスなんかと・・・・・・・・・・・・・。
「いらないなら無理に飲まなくていいけど。・・・エース、いったいどうしたの?
具合悪い?」
タンクトップから剥き出しの俺の二の腕にあいつがそっと手をかけた途端、
いきなり身体に電流を流されたように、俺の身体は硬直した。
触れた部分がぴりりと緊張して、苦い痛みが全身を駆け巡る。
腋の下にじっとりと滲む、嫌な汗。
サワルナ。
ミルナ。
ソバニクルナ。
ソレイジョウチカヅケバ・・・・・
寝苦しい熱帯夜の明け方に見る、なかなか終わらない変にリアルな悪夢みたいに、
得体の知れない凶暴な感情が、突然ドロドロと渦を巻いて、俺を飲み込む。
ソレイジョウチカヅケバ・・・・オレハオマエヲ・・・・
オレハオマエヲ・・・・・・・・・・・・・メチャクチャニシテシマウカモシレナイ。
「・・・・・・・・・・・帰るっ」
「エース?!」
昨日はシャンクスの胸にそっと置かれていた、綺麗に爪を切りそろえたその指先を振り払い、
俺は一度も振り返らずに店を後にした。
もっともっとガキの頃は、ルフィの奴と争って、よくあいつの膝によじ登った。
柔らかい腕が身体に巻きつくと、あったかくてくすぐったくて、俺たちは声を立てて笑った。
甘く優しい日々の記憶。
知らない女の知らない手。
あれは・・・・・・マキノだけど、マキノじゃない。
俺の知らない、とてもよく似た別の女。
もう・・・・・あの頃のマキノには二度と会えない・・・・。
どこをどう走ったのか、気付くと俺は、港を見下ろす丘に登っていた。
吹き上げる浜風に前髪を嬲られながら、低い潅木の幹に手をかけて、呼吸を整える。
ルフィはシャンクスの後を追いかける。
マキノはシャンクスとキスをする。
そして俺ひとりが・・・・すり替えられた世界の中で、いつまで馴染めない異物のまま
足掻き続けなければならないのか。
生い茂った夏草に腰を下ろし、遥か遠くに目を凝らすと、眼前に広がる青い海原は、
まるで果てなど無いかのごとく、どこまでも広がり続けている。
海に、出よう。
そして一人で・・・・この波の彼方にあるものを見に行こう。
知らず知らずに熱いものが込み上げ、訳も分からず俺は涙を流し続けた。
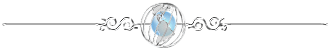
「お待たせ、隊長さん。・・・・・・・・・・どうかした?」
「いや、なんでもねえよ。さあ、乾杯しよう。グラスくれよ。」
「いいけど、何に?」
「・・・・・・・過ぎ去りし我が少年の日の輝きに。」
おどけた調子で勢いよくグラスを合わせると、なみなみと注がれたライムジュースが揺れる。
重く湿った闇が身体に纏わりつき、蒸し暑い夏の夜は、まだまだ明ける気配を見せない。
幾度こんな夜を越えれば、俺はあの日目指した夢の到達点に辿り着くことが出来るのか。
この世の果ては・・・・・・未だ漆黒の宵窓の向こう。
ガリリと氷を噛み砕くと、今はもう会えない人の優しい笑顔が、少しだけ俺の胸を焦がして消えた。
END
![]()
尚美さんがサイト開設祝い第1段に下さいました。
最初のシーンにどきどき(馬鹿)したのは私一人ではないはず。
きちんとしたしっかり者の一番隊隊長さんの
暑い思い出が氷の入ったライムジュースに・・
幼い日の憧憬がしっとり伝わる尚美さん流のシャンマキ←エース
ありがとう!!らっこちゃん!
ライムは尚美さん仕様にブルーにしてみました。